2025
5/14

ある飲みの席にて
「ウチの情シスメンバーはまったく使えない。全員クビにして、優秀な人を連れてきたい⋯」
ある夜、ある現場の情シス部長と飲みにいきました。お酒も入り、ざっくばらんな雰囲気の中で、彼がポツリと漏らしました。
もちろん、アルコールが入りすぎて感情が先走ったのはわかっています。普段の彼は、部下に丁寧に接する真面目な方です。それでも、DX志向の部長として、改革に燃えています。その分、現場との温度差にフラストレーションを抱えていたのでしょう。
彼のような「攻めのIT人材」から見ると、「守りのIT人材」はどうしても物足りなく見えてしまいます。マイペースで、同じルーティンを繰り返しているだけ。自分の方が何倍も苦労して、頑張っているように感じます。
「もっとタスクを持ってよ」「サボらないでよ」と思ってしまいます。
とくに「守りから攻めにシフト」を真剣に考えている情シス部長には、ギャップが目についてしまいます。それは、仲間への失望、孤立へと進みかねません。
物足りないと感じるメンバーとは、どう向き合っていけばよいのでしょうか?
かつて私も「信じないコンサル」だった
私は、かつての現場を思い出します。
若かりし私は、ある現場の基幹システムプロジェクトに保守メンバーをアサインし、一緒に進めました。しかし、そのメンバーが作る資料は使えず、説明も要領を得ない。結局、私がすべてを巻き取って進めるハメに⋯。私はその人が「使えない」と思いました。そのメンバーは3ヶ月でプロジェクトを離脱しました。いや、追い出したようなものです。
ところが、その彼が別の業務システムプロジェクトに参加したとき、現場の信頼を一身に集める存在になっていました。しゃべるのは相変わらず苦手でしたが、現場リーダーがそこはうまくフォローしています。現場からの無茶な依頼にも淡々と応え、手を動かして形にする力は本物でした。
私はようやく気づきました。彼は「使えない」のではなく、そのときの役割が適切でなかっただけ、だと。その人が活躍できるようなサポートが私に足りなかったのだと。
「自分が得意としていることは、相手もできて当然」という、価値観の押し付けがありました。自分とのギャップが、やたら目につき、許せない自分がいました。
自分の未熟さに気付くまでに、ずいぶんと時間もかかってしまいました。信じる力、待つ力、そして見抜く力。どれも足りなかったのです。
むしろ自分ができないことができる
得てして、ヘルプデスクや運用保守担当は、クリエイティブ系やプロジェクト型の人から誤解されやすいものです。
「毎日、同じことしかしていない」
そう思われがちですが、じゃあ逆に
あなたはその仕事をできますか?
クリエイティブ系やプロジェクト型の人にとって、それは最も苦手とするタスクでしょう。1ヶ月もたないのではないでしょうか。
ルーティン業務には、安定と継続に価値があります。現場は、その人がいるから安心して業務に専念できています。それが得意な人は、そこを全うしてもらえばいいのです。それは良い悪いではなく、適材適所の問題です。
また、今はそれをやっているけれども、チャンスを与えたら「覚醒」するかもしれません。それはやってみないとわかりません。
自分にない能力をもっている。
そう捉えるとリスペクトの気持ちが生まれます。相手もそれを敏感にキャッチします。すると、少しずつ関係性が変わってきます。
長い目で見る
確かに、組織としては「守り」だけではなく、「攻め」へと舵を切る必要があります。ノンコア業務からコア業務へ、運用型から戦略型へ。
でも、それには時間がかかります。世代交代を含めて、広い視野で、あらゆる選択肢を持ちながら、ロングスパンで考えなければなりません。
かといって、頑張らないメンバーを完全に野放しにしたり、好き放題させたりするのも違います。風紀が乱れ、真面目に頑張っている人のモチベーションを損なうからです。
真面目に頑張っている人は、正当に評価していきましょう。頑張っていない人には、改善目標を出させて、改善を促していきましょう。
組織はグラデーションで変わる
組織は急には変えられません。だからこそ、設計にはバランス感覚が必要です。
自分と違うタイプだったとしても、それは自分にはない特性をもっているということ。ならば、その特性が生きる役割を与え、全うしてもらえばいいのです。同時に、その特性に見合ったチャンスも与えてみて、全力でフォローする。うまくいけば、その方向にシフトし、ダメだったらもとに戻す。その試行錯誤です。
その上で、次の採用や配置転換では、攻めの人材を配置し、少しずつ色を変えていく。守りは自動化やアウトソーシングに移管していく。
気がつけば、組織は自然とノンコアからコアへとシフトしていきます。焦らず、でも確実に。
それが、情シス改革の「現実的な進め方」なのだと思います。
次に採用する人材を「攻め」に変える前に、いまいる人材の「適材適所」を見直してみる。信じて任せることで、覚醒が起きるかもしれません。
現有戦力でやるしかない
なんだか私が聖人っぽくなってしまったので、私の本心も書きます。
正直に言えば、冒頭の情シス部長の気持ちは、私にもよくわかります。むしろ、私もそっち側です。
仕事の生産性を上げて、さらにレベルアップするために、プライベートの時間を削って、学び続ける。人より多くの本を読み、セミナーで聞いた話を持ち帰っては、試行錯誤する。
だから、勤務時間内に多くの休憩時間を挟んだり、昼休みからなかなか帰ってこなかったり、無駄に長電話したり、のらりくらりやったりしている人を含めて「情シス」と一括りにされるのは、納得しがたい。
その人の仕事の遅さのせいで、こっちにしわ寄せがきて、余計にタスクが増える。トラブルが起きたときには、自分がケツを拭く羽目になる。
理不尽でしょう(苦笑)。
でも・・・、とはいえ・・・、誰かをクビにしても、すぐに理想とする人材を補充できるわけではない。結局はクビにした人にシワ寄せがくる。そもそもクビにできない。つまり、人は簡単には入れ替えられない。これは、いかんともしがたい事実です。組織で働く以上は、前提となります。
この当たり前を認めることに、私は長い年月がかかりました。
情シスという組織は、「現有戦力」でやるしかないんです。
だからこそ、今いるメンバーでどう戦うか。どうやって持ち味を引き出し、どうチームとして整えていくのか。それが情シス部長の「腕の見せ所」です
まずは、開き直る。覚悟を持つ。尊敬する。そしてチャンスを与える。待つ。寛容になる。
絶対に、人間としての器が大きくなりますね!
コラム更新情報をメールでお知らせします。ぜひこちらからご登録ください。
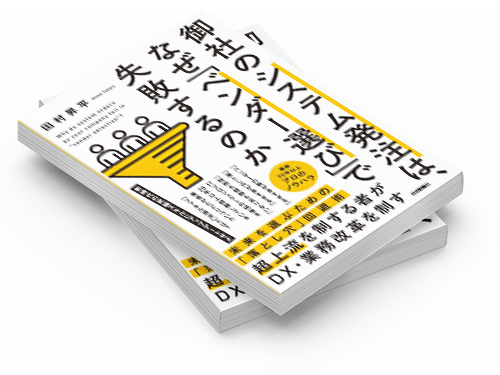
情シスコンサルタント
田村 昇平
情シス(IT部門、情報システム部門)を支援するコンサルタント。
支援した情シスは20社以上、プロジェクト数は60以上に及ぶ。ITベンダー側で10年、ユーザー企業側で13年のITプロジェクト経験を経て、情シスコンサルティング株式会社を設立。
多くの現場経験をもとに、プロジェクトの全工程を網羅した業界初のユーザー企業側ノウハウ集『システム発注から導入までを成功させる90の鉄則』を上梓、好評を得る。同書は多くの情シスで研修教材にもなっている。
また、プロジェクトの膨大な課題を悶絶しながらさばいていくうちに、失敗する原因は「上流工程」にあるとの結論にたどり着く。そのため、ベンダー選定までの上流工程のノウハウを編み出し『御社のシステム発注は、なぜ「ベンダー選び」で失敗するのか』を上梓し、情シスにインストールするようになる。
「情シスが会社を強くする」という信念のもと、情シスの現場を日々奔走している。
著書の詳細は、こちらをご覧ください。