2025
5/21

生成AIを使わせたくない社長
「生成AIを新人に使わせたくないんだよ」
ある会社の社長とランチをご一緒しました。かつて、基幹システム導入を支援した会社で、今でも年に数回、情報交換も兼ねて食事をご一緒しています。
その席で、このような話が出ました。
「生成AIには興味がある。私も実際に使ってみて、脅威を感じるほど優れていた。だが、社員に使わせてよいのか悩んでいる」
なぜですか?と聞きました。
「社員が自分で考えなくなるから。特に新人には危険だな〜。ベテランは自己判断できるからいいけど、若手を育てるには悪影響なんじゃないか」
その懸念はよくわかります。たしかに、何でもAIに聞けば答えてくれます。
使えば使うほど、人間がどんどん「骨抜き」になる。考えなくなり、判断力も育たなくなる・・・。
ですが、それを理由に生成AIの導入をストップしてしまって良いのでしょうか?本当に、それが「人を育てる」ことになるのでしょうか?
電卓、Google検索、生成AI
「その話、昔の『電卓』と同じですよね」
私はそう返しました。電卓が登場したとき、私は小学校の先生から「電卓禁止!」「バカになる!」と言われました。
たしかに、子どものうちは、自分で計算力を鍛えることは大事です。当時のその指導は正しかったと思います。
一方で、職場においても電卓禁止にするのでしょうか?
むしろ使わなかったら「なんでそんな非効率なことをしているの?」となります。他社に置いていかれるだけです。計算の速さや正確さは、いまや「競争領域」ではありません。そこはツールにまかせて、その先の仕事に頭を使うのが当たり前です。
Google検索も同様です。
かつて「調べ方を知らない若者が増えている」と言われました。しかし今では「検索」は仕事の基本動作です。使いこなせないと、むしろ「情報を調べられない人」と扱われてしまいます。
生成AIも、同じ道を歩むのではないでしょうか。
重要なのは「生成AIがある世界」で、どう成果を出せるかという視点です。そこでは、出力された情報をうのみにせず、「問い直し、判断する力」が問われます。新人教育こそ「AIを正しく使う力」を鍛えるチャンスなのかもしれません。
しかし、社長はまだ腑に落ちていない様子でした。
生成AIは考えない人を置き去りにする
「う〜ん、たしかに『取捨選択する力』は鍛えられるよね。でも・・・やっぱり『考える力』が育つイメージが沸かないんだよな〜」
たしかに、その不安も理解できます。でも、私は生成AIを日常的に使っているからこそ断言します。
考えずに丸投げしても、良いアウトプットは絶対に得られません。深く考えているかどうかは「プロンプト(指示文)」に現れるからです。思考が浅ければ、プロンプトも抽象的で曖昧になります。その結果、出力された内容もどこかズレていて、核心をついていないのです。
しかも厄介なのは、表面的には「それっぽく」見えてしまうこと。そして、そのアプトプットが脳内に「固着」してしまい、それが唯一の答えのように見えてしまうこと。たとえそれが大きく間違っていたとしても、もう別の考えができないぐらい、思考が縛られてしまいます。
それが怖いのです。深く考えていなければ、そこから抜け出すことができません。それが正しいかどうか、まったく判断できないからです。出力を制御できず、振り回されるだけです。その結果、そのまま「コピペ」して、後で赤っ恥をかく羽目になります。
つまり、生成AIを使えば使うほど「考えていない人」が恥をかくのです。
Google検索と同様に、生成AIの利用も「当たり前」の世界になりつつあります。
むしろ自由に使わせる。ただし、新人の成果物は、上司や先輩が「いつもどおり」レビューする。そこで考え抜かれていないアウトプットは浅いので、すぐに見抜かれる。説明を求められても、何も答えられず、カンニングがバレる。やり直しを命じられる。
AIに丸投げすれば、成果が出ない。怒られる。恥をかく。
そのうち、新人自身が「これは使い方を間違えている」と気づき始める。そこから、自分なりに考えるようになる。質問の切り口を何通りも試し、自分の中での「思考実験」を繰り返す。
つまり、深く考えるように自然と誘導されていきます。
こちらが細かく言わなくても、生成AIを使えば使うほど「考えない人」は置いていかれる。そして、「考える人」がどんどん伸びていく。
これは生成AIに限らず、すべてに言えるのではないでしょうか。
より本質的な成果主義へ
運用ルールは何も変えない。生成AIを使おうが使うまいが、新人の成果物は上司や先輩がレビューするだけ。
ただそれだけで、考えている人と考えていない人の差が明確になります。
社長が言いました。
「なるほど、確かにそうかもしれない。成果主義でいいんだよ。結果で判断すればいいだけの話だな」
さすが、経営者らしい返しです。
先般、テレワークの浸透でプロセスが見えにくくなったため「成果主義」が加速したと言われています。しかし、生成AIによって、成果主義はますます加速していくのではないでしょうか。
仕事をしていないのにダラダラ残業だけして「頑張ってるアピール」は通用しません。テレワークで深夜に「了解しました」とだけ返して、「まだ仕事してます感」を演出しても、評価されなくなります。
これからは、自分の頭で考え、自分なりの「問い」を立てて、ツールを使いこなし、成果に結びつけられる人が、生き残っていきます。
それは、生成AIでも、電卓でも、Google検索でも変わりません。
「むしろ生成AIで『生産性3倍』とかの方が面白くないですか?」
と最後は盛り上がりました。次回にお会いするのが楽しみです!
コラム更新情報をメールでお知らせします。ぜひこちらからご登録ください。
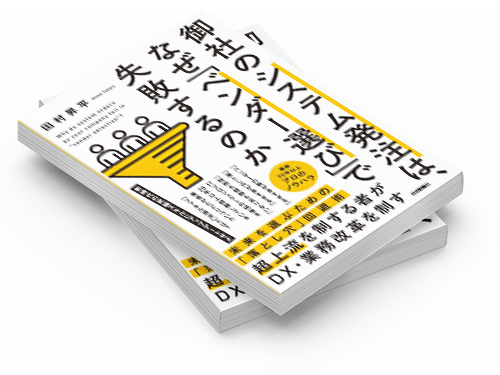
情シスコンサルタント
田村 昇平
情シス(IT部門、情報システム部門)を支援するコンサルタント。
支援した情シスは20社以上、プロジェクト数は60以上に及ぶ。ITベンダー側で10年、ユーザー企業側で13年のITプロジェクト経験を経て、情シスコンサルティング株式会社を設立。
多くの現場経験をもとに、プロジェクトの全工程を網羅した業界初のユーザー企業側ノウハウ集『システム発注から導入までを成功させる90の鉄則』を上梓、好評を得る。同書は多くの情シスで研修教材にもなっている。
また、プロジェクトの膨大な課題を悶絶しながらさばいていくうちに、失敗する原因は「上流工程」にあるとの結論にたどり着く。そのため、ベンダー選定までの上流工程のノウハウを編み出し『御社のシステム発注は、なぜ「ベンダー選び」で失敗するのか』を上梓し、情シスにインストールするようになる。
「情シスが会社を強くする」という信念のもと、情シスの現場を日々奔走している。
著書の詳細は、こちらをご覧ください。