2025
11/12
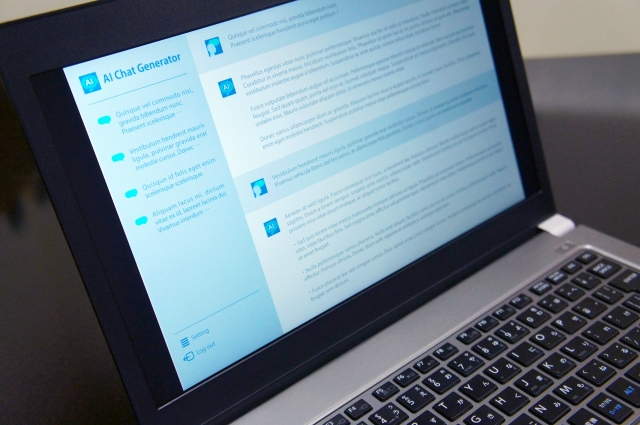
実はあまり使っていない情シスPMO
「情シスが、あんまり使ってないんですよ」
ある企業の情シス部長が、少し苦笑いを浮かべながら話してくれました。
その会社では、全社的に「生成AI」の導入と活用が進められており、現場に対する啓蒙活動も盛んに行われています。eラーニングも整備され、使い方マニュアルやプロンプト例まで配布されていました。
ところが、蓋を開けてみると、肝心の情シスPMOメンバーがほとんど活用していません。
確かに、内製開発チームであればコード自動生成等が便利なので、生成AIの「わかりやすい使い道」が豊富にあります。
しかし、プロジェクト活動は、打ち合わせや社内調整、ベンダー対応などがメインであり、あまり生成AIを活用する余地がないとのこと。
いやいや、それは大きな誤解です。むしろPMOこそ、生成AIのポテンシャルを最大限に引き出す多様な活用シーンがあります。
では、具体的にどのような活用シーンがあるのでしょうか?
PMOの活用シーン
例えば、ベンダー選定の場面。
「営業支援システムのベンダー選定を行いました。落選したベンダーにその旨を伝える、失礼のないメール文を作成してください。」
そう依頼すると、生成AIは次のように答えてきます。
件名: 営業支援システムベンダー選定結果のご連絡
〇〇株式会社
〇〇部 〇〇様
平素より大変お世話になっております。
〇〇株式会社の〇〇です。
このたびは、弊社の営業支援システム導入に関するご提案をいただき、誠にありがとうございました。
慎重に検討を重ねた結果、今回は他社様の提案を採用させていただくこととなりました。
貴社にはお忙しい中、ヒアリングやお見積り対応など多大なご尽力を賜り、心より感謝申し上げます。
貴社のシステム・ご提案内容は非常に有意義であり、今後の参考とさせていただきたいと考えております。
今後、別のプロジェクト等でご一緒できる機会がございましたら、ぜひ改めてご相談させていただければと存じます。
引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
敬具
ご希望があれば、もう少しカジュアル(社内ベンダー向け)やフォーマル(大手SIer向け)に調整したバージョンもお出しできます。どちらのトーンで仕上げましょうか?
このような文案をベースに、プロジェクト特有の事情を加筆修正するだけで、ゼロから作るよりも早く、かつ丁寧な文章が完成します。
他にも、以下のような問いかけで、プロジェクトのさまざまな場面を支援できます。
「ノーコードツールが社内に浸透していません。普及施策を5つ考えてください」
①「最初の成功体験」を演出するミニプロジェクト
目的:現場が「自分たちにもできる」と実感すること。
施策内容:一部門を選び、30分以内で効果が出るミニ自動化(例:日報集計・棚卸リマインド)を一緒に構築。
ポイント:「最初の成功例」を社内イントラや掲示板で紹介し、他部門に波及させる。
②「ノーコード活用コンテスト」の開催
目的:自発的な参加と横展開を促す。
施策内容:
・テーマ:「現場のムダ削減」や「日常業務の自動化」など。
・優秀作品は社内報・表彰・経営会議で紹介。
ポイント:アイデアだけでも応募可能にして、「作れない人も参加できる」設計にする。
③「お助けチーム」設置とワンポイント支援
目的:現場の“詰まり”を早期解消。
施策内容:情シス+現場経験者で構成する「ノーコードお助け隊」を設け、1on1サポート。
ポイント:TeamsやSlackに「#ノーコード相談室」チャンネルを常設して、質問しやすくする。
④「テンプレート&部門別活用例」カタログ化
目的:ゼロから作る心理的ハードルを下げる。
施策内容:
・社内共通テンプレート(申請フロー、日報、集計)を整備
・部門別活用例(営業、総務、経理)を一覧化
ポイント:「作る」より「選んで直す」だけで済む状態をつくる。
⑤「人事評価・表彰制度」との連動
目的:行動のインセンティブ化。
施策内容:「ノーコード活用による業務効率化」を人事評価項目や社内表彰に組み込む。
ポイント:上司が「ツール活用を推奨する動機」を持てるようにする。
ご希望があれば、これらを「導入初期」「定着期」「拡大期」の3段階に分けたロードマップ(時系列表)として整理することもできます。
その形にして出力しましょうか?
「3か月後に本稼働を迎える基幹システム。本稼働判定項目を挙げてください」
以下に、実務で使いやすい形で整理します。
本稼働判定項目一覧(カテゴリ別)
(※ 長いので、以降省略 ※)
「要件定義完了後、ベンダーPMが交代しました。どう対応すべきかアドバイスをください」
要件定義完了後のベンダーPM交代は、プロジェクトの「温度」や「文脈」が途切れる最大のリスクポイントです。
以下に、実務的な対応ステップを5段階で整理します。
① 現状把握とリスク評価を最優先
まず「交代理由」と「引継ぎ範囲」を正確に把握してください。
交代理由の確認:病気・異動・能力不一致・契約変更など。
→ 理由によって、リスクの大きさが異なります。
引継ぎの深度確認:
・要件定義成果物(要件定義書・課題一覧・議事録)
・非公式の合意(口頭・チャット・Excelメモ)
・業務部門の意図や背景の共有度
ポイント:
単に「資料を引き継いだ」では不十分です。要件の背後にある「業務上の意図」や「優先順位」が抜け落ちていないかを必ず確認。
(※ 長いので、以降省略 ※)
「本番稼働後に障害が多発。品質不足の責任をどうベンダーに問うべきか?」
「品質不足の責任を問う」場合、感情的・抽象的に責めると関係がこじれます。
一方で、曖昧なまま放置すれば、次も同じ過ちを繰り返します。
したがって、“責任追及”よりも“責任構造の整理と再発防止要求”という形で進めるのが最も効果的です。
以下、実務で取るべきステップを5段階で整理します。
① 事実の整理と「責任範囲」の明確化
まず、感情よりもファクトをベースに構造化してください。
ポイントは「何が起きたか」より「どの工程で防げたか」です。
(※ 長いので、以降省略 ※)
これらはすべて、PMOが日常的に直面する悩みです。そして、生成AIに「壁打ち」すれば、ある程度の方向性やたたき台をすぐに得られるのです。
PMOのほぼすべての活動で活用できる
生成AIの活用シーンを、PMOの業務領域に即して分類してみましょう。
・システム企画書作成
・プロジェクト計画書作成
・RFP作成
・本稼働判定表作成
・候補ベンダーリスト作成
・アジェンダ作成
・議事録作成
・メール文案作成
・調査レポート作成
・障害管理グラフ化
<ベンダー成果物レビュー支援>
・要件定義書レビュー
・移行計画書レビュー
・設計書レビュー
<プロジェクトの進め方相談やアイデア出し、壁打ち>
・活用アイデア出し
・リスク洗い出し
・障害多発時の対応案
・モチベーション向上施策案
・プロジェクト問題の相談
・検索・調査・調べ物
「生成」という言葉から、なにかの「文案」や「ドラフト資料」を作ってもらうという発想はすぐに出てくると思います。
それだけではなく「プロジェクトの専門家に相談する」「アドバイスをもらう」「チェックしてもらう」という発想を持てば、活用範囲は一気に広がっていきます。
つまり、PMOの「ほぼすべての活動」で、生成AIは活用できるのです。
情シスPMOに求められる姿勢とは?
「こんなに便利なんですね。これからどんどん使おうと思います!」
先日、情シスPMOメンバーを集めて、勉強会を実施。私が用意した20種類のプロンプトを実際に入力してもらい、その便利さを実感してもらいました。
PMOにとって重要なのは、「スピード」と「質」を両立させること。
生成AIを使えば「たたき台」が爆速で出てきます。その分、検討や確認に時間を割くことができ、品質はむしろ向上します。
ただし、口酸っぱく申し上げたのは「丸投げしてはいけない」ということ。
出力結果は、情シスPMOが責任をもって判断する必要があります。そのまま採用するのか、アレンジを加えるのか、あるいは出力し直すのか。こうした判断は、主体性をもって行わなければなりません。
生成AIが瞬時に多くのアイデアを出し、人間が最適を選び取る。この「役割分担」ができている限り、生成AIはPMOにとって大きな助けになります。
それにより、関係者との打合せや進捗確認といった「対面の仕事」に、より多くの時間を使えるようになります。これこそ、プロジェクトの本質的な成功に直結します。
情シスPMOこそ、生成AIを味方にすべきです。それだけで、情シスPMOの生産性と信頼性は大きく変わってきます。
貴社のIT部門・情報システム部門は、プロジェクト活動で生成AIを使い倒していますか?
コラム更新情報をメールでお知らせします。ぜひこちらからご登録ください。

情シスコンサルティング株式会社
田村 昇平
情報システム部門(情シス)を起点に、経営戦略とDXを統合するコンサルタント。
システム開発を10年、ユーザー側のITプロジェクト支援を13年。ベンダーとユーザー、双方の立場を経て独立。これまで30社以上、100を超えるプロジェクトに携わる。
近年は、現場主導のDXが行き詰まる企業が多い現実を踏まえ、「経営主導」への転換を提唱。トップダウンでDX戦略を策定し、実行可能な形で「仕組み化」する支援を行っている。併せて、「情シスをDX推進の中核組織」へと進化させる独自メソッドも確立してきた。
膨大な現場経験での数多くの失敗や板挟みとなる葛藤。それらを乗り越えてきた知見をもとに、机上論ではない「再現性のあるDX」を追求する実務家として、経営者・CIO・情シス部長と伴走している。
主な著書に『システム発注から導入までを成功させる90の鉄則』『御社のシステム発注は、なぜ「ベンダー選び」で失敗するのか』『DXで経営戦略を仕組み化する技術』がある。
著書の詳細は、こちらをご覧ください。