2025
5/07

経営層からの指摘
「利用シーンが不明確で計画書と言えるのか?」
「そんなフワッとした目的で、稟議を通せると思っているのか?」
ある現場で、情シスメンバーが「生成AI導入計画書」を経営層に説明しました。しかし、このような助言?を頂戴し、計画書は突き返されます。
これまでのシステム導入では「何のために導入するのか」「どのように利用するのか」「どんな効果が期待できるのか」を事前に明確にし、計画書に落とし込むのがセオリーでした。
一方で、生成AIについては、このように綿密な計画書を作成しようとすると、逆にうまくいかないケースが多く見受けられます。なぜでしょうか?
生成AIの本質
たとえば、20年以上前に、現場に「Excel」を導入することをイメージしてください。Excelは非常に便利なツールですが、「この関数だけ使いなさい」「この業務だけに使ってください」と用途を限定してしまうと、どうなるのでしょうか?生産性の向上は、その範囲にとどまってしまいますよね。
むしろ、ある程度自由に使わせてみることで、「こういう使い方もできる」「こうすればもっと効率化できる」といった発見が現場から次々に生まれます。
生成AIもまったく同じです。
生成AIの本質は「利用の幅」と「自由度」にあります。様々な活用の余地が残されているからこそ、全体としての生産性向上が期待できるのです。
それなのに、導入の時点で使い方が「決め打ち」されてしまうと、それ以外の使い道が試されなくなります。その結果、「思ったより使えない」という評価につながってしまうのです。
さらに、生成AIという技術自体が、今なお日進月歩で進化しています。今日はイマイチだったものが、来月のバージョンアップで普通に使えるようになっている。そんなことが当たり前のように起きています。
つまり、今日の「前提」が、来月には崩れてしまうのです。
環境構築が目的でもいい
従来のシステム導入では、「明確な目的」「利用シーン」「効果」が必須でした。それ自体は、合理的な進め方といえます。
しかし、生成AIにおいては、まず「環境を整える」こと自体が、立派な目的となるのではないでしょうか。
・社員が使える状態にする
・情報漏洩リスクを考慮したルールを整備する
・学びやノウハウ、実績が共有できる仕組みと文化を醸成する
そして、生成AI導入の最初の目標は「全社員が生成AIを活用する習慣を身につける」ことにあります。毎日触ることで
「こういう聞き方をすると、意外に使える」
「この用途は向いていないけど、別の切り口ならいける」
といった感覚が積み重なり、やがて大きな気付きにつながっていきます。
また、他社の成功事例にも敏感になり、「ウチならこう応用できそうだ」と自社の文脈に置き換えて、考えられるようになります。
毎日使っているからこそ、生成AIの「勘所」が養われます。
失敗したアイデアや雑多な情報の中から、ある日ふと「これだ」と思える突破口が見つかる。そういった偶発的な発見を促す「土壌」を整えることが、生成AIの導入フェーズでは、もっとも重要な観点だと考えます。
まずは使ってみる
「アイデアコンテストを社内で開催します!」
冒頭の現場は、生成AIの導入計画書を作り直しました。「現場の知見と創造性を引き出し、生産性を上げる」というコンセプトを前面に押し出し、ようやく経営層から承認されました(⋯なかなか苦労しましたけれども・苦笑)。
生成AIをDXにつなげたいなら、まずは「構想」よりも「慣れ」です。
・いつでも試せる環境を用意すること
・トライアンドエラーが許容される文化を育てること
・自由な発想を評価し、改善につなげる制度を整えること
まずは使ってみましょう!そこから、DXが動き出します。
あなたの会社では、生成AIに慣れる前に、いきなりアイデアを固定して、ガチガチな計画を立てていないでしょうか?
コラム更新情報をメールでお知らせします。ぜひこちらからご登録ください。
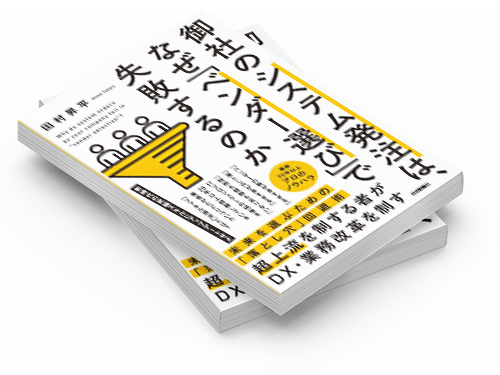
情シスコンサルタント
田村 昇平
情シス(IT部門、情報システム部門)を支援するコンサルタント。
支援した情シスは20社以上、プロジェクト数は60以上に及ぶ。ITベンダー側で10年、ユーザー企業側で13年のITプロジェクト経験を経て、情シスコンサルティング株式会社を設立。
多くの現場経験をもとに、プロジェクトの全工程を網羅した業界初のユーザー企業側ノウハウ集『システム発注から導入までを成功させる90の鉄則』を上梓、好評を得る。同書は多くの情シスで研修教材にもなっている。
また、プロジェクトの膨大な課題を悶絶しながらさばいていくうちに、失敗する原因は「上流工程」にあるとの結論にたどり着く。そのため、ベンダー選定までの上流工程のノウハウを編み出し『御社のシステム発注は、なぜ「ベンダー選び」で失敗するのか』を上梓し、情シスにインストールするようになる。
「情シスが会社を強くする」という信念のもと、情シスの現場を日々奔走している。
著書の詳細は、こちらをご覧ください。