2025
7/24

本稼働後のベンダー協議
「プログラムバグは無償で対応する義務がありますよね?」
情シスメンバーは、誰もがその言葉を今にも口にしそうでしたが、我慢しました。
ある現場で、本番稼働後にバグが次々と表面化し、その状況が数ヶ月も続いています。ここでいうバグとは「プログラムバグ」です。
「システムエラー」と表示され、処理が止まってしまったり、画面と帳票で数字が異なっていたり、特定条件下で画面がフリーズしたり、明らかに「テスト不足」と思えるようなバグが多く発生しています。
ついに我慢の限界がきた経営幹部とプロジェクトメンバーがベンダー責任者を呼び、今後の方針を話し合いました。ユーザー側からの「ベンダー責任を問う!」という厳しい空気が、会議室を包み込んでいます。
ベンダー責任者は申し訳なさそうに状況を謝罪し、真摯な対応を約束しました。そこまでは全員が合意しています。
しかし、問題は今後発生するバグ対応の「費用負担」です。
当初予定していた3ヶ月の「安定稼働支援」期間が終わり、これから「保守フェーズ」に入ます。ベンダー体制を薄くし、費用を抑える計画でした。
「この品質状況で体制を薄くするなど、とんでもない」
誰もがそう思ったでしょう。ベンダーも頭を下げ、「体制維持のために追加費用をお願いできないか」と懇願してきました。
ベンダーが最大限に対応してくれているのは、わかっています。連日徹夜しているのも知っています。これ以上追い詰めては、ベンダーが潰れるか、保守撤退という最悪のシナリオも見えてきます。
でも、バグが大量に発生しています。新システムの「品質不足」はまぎれもない事実です。ベンダーが責任をもって対応するべきでしょう。
ただ、そこに対して「追加費用」を払うことに大きな抵抗感があるのです。
特に、致命的なバグが発生して、営業担当が客先で謝罪を繰り返すシーンを目の当たりにすると、ユーザー側の苦しみがさらに伝わってきます。
この状況で、情シスPMOはどのように対応すればいいのでしょうか?
正論だけではプロジェクトは成功しない
バグの無償対応は「契約不適合責任」であり、正論です。
ユーザー側としては、バグはベンダー責任として対応を要求するのは当然のことです。ベンダー責任者も反論はできません。
そのシーンだけを切り取れば、正解でしょう。
しかし、プロジェクトは正論だけで片付きません。これまでの経緯や、環境変化、人間関係、契約内容といった複雑な要素が絡んできます。
ここで正論だけを振りかざし、ベンダーを責めて溜飲を下げるのは短期的にはスッキリするかもしれません。しかし長期的には正しいのでしょうか?
遡ってみると、そもそもプロジェクトが遅れた原因は、ユーザー側にもありました。
テストの遅延、仕様変更のねじ込み、これらをベンダーは受け入れてきました。受け入れテストを十分に行う余力がなく、潜在バグの検出が甘かった部分も否めません。そこに対して、バグの即時対応というさらなる負荷を押し付けている状況ともいえます。
もっと遡れば、ベンダー選定時に競合他社より大幅に安価な見積もりを出してきました。そのため、費用を大幅に抑えることができて、今に至ります。
ベンダーは言いませんが、採算が取れずに苦しい状況にあることは容易に想像がつきます。それにも関わらず、ユーザーが強気の値引きを要求し、なんとかその価格で対応しようとしてくれました。
そのユーザーが今になって「バグはベンダー責任」と、鬼の首をとったかのように主張することに、違和感を感じます。
このままバグの無償対応だけを求め続ければ、さらにサービス品質が落ち、最終的にユーザー側が困る状況にもなり得ます。関係が悪化すれば、今後の保守契約で不利になったり、逃げられるリスクもあります。最悪、ベンダーが倒産する可能性もあります。
この状況下で、情シスのPMOメンバーは客観的な判断が求められます。双方の立場を理解した上で、落とし所を探る必要があります。
経営判断を仰ぐ
その後、PMOメンバーは「経営トップ」に状況を正直に報告しました。
現在の品質状況だけでなく、ユーザー側の不備、ベンダーの努力、低価格での対応、追加費用がかかってもトータルで安いこと。
もし、ここでベンダーを追い込めば、代替ベンダーを探す費用や新たな移行リスクが発生し、結局は高くつくこと、なども伝えました。
経営トップは静かに聞いています。そして一言、「それは追加契約だろう」と決断しました。長期的なパートナーシップを構築し、お互いに発展していこうという前向きな「経営判断」です。
情シスメンバーは、感情に流されず、ベンダーを一方的に非難しなくて良かったと、胸をなでおろしました。
ユーザーも不満はありましたが「経営トップの判断だから」と、それ以上は言わなくなりました。自分たちにも落ち度があり、ベンダーが頑張っていることも知っていたからです。複雑な感情を抱えつつも、成功に向けて再び気持ちを切り替えていました。
バグに対して、追加費用が正しいと主張するつもりはありません。複雑な状況の中で、今回はこの判断に至っただけです。
プロジェクトは、なかなか教科書通りにはいきません。状況は毎回異なり、その都度、最適な判断を総合的に考える必要があります。感情的な即決は避け、関係者の状況を配慮した上で判断すべきです。
いつも判断は「紙一重」だと感じます。正解がない中で、正解にもっとも近いであろうものを選択、判断していく。情シスPMOが最後まで思考停止せずに、踏ん張るからこそ、プロジェクトはギリギリのところで、最後は何とかなるのではないでしょうか。
ベンダーと再度の打ち合わせ
「全力で対応します」
後日、再度ベンダーと話し合います。追加契約を伝えると、ベンダー責任者は目を閉じて、一呼吸しました。そして、こちらの目を見て、決意表明のように静かに答えました。
プロジェクトは、利害関係者の対立がつきものです。だからこそ、情シスは当事者であるユーザーとベンダーから一歩引いて、俯瞰的に捉えていくことが求められます。
貴社のIT部門・情報システム部門は、本番稼働後のユーザーとベンダーとの関係をうまくコーディネートできていますでしょうか?
コラム更新情報をメールでお知らせします。ぜひこちらからご登録ください。
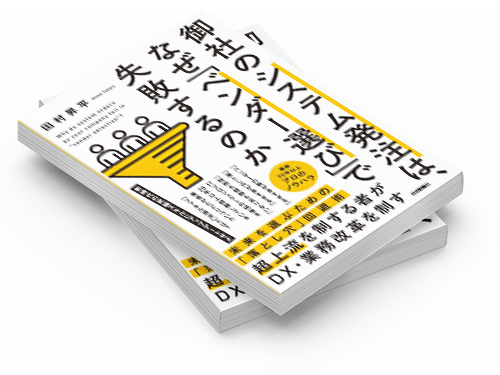
情シスコンサルタント
田村 昇平
情シス(IT部門、情報システム部門)を支援するコンサルタント。
支援した情シスは20社以上、プロジェクト数は60以上に及ぶ。ITベンダー側で10年、ユーザー企業側で13年のITプロジェクト経験を経て、情シスコンサルティング株式会社を設立。
多くの現場経験をもとに、プロジェクトの全工程を網羅した業界初のユーザー企業側ノウハウ集『システム発注から導入までを成功させる90の鉄則』を上梓、好評を得る。同書は多くの情シスで研修教材にもなっている。
また、プロジェクトの膨大な課題を悶絶しながらさばいていくうちに、失敗する原因は「上流工程」にあるとの結論にたどり着く。そのため、ベンダー選定までの上流工程のノウハウを編み出し『御社のシステム発注は、なぜ「ベンダー選び」で失敗するのか』を上梓し、情シスにインストールするようになる。
「情シスが会社を強くする」という信念のもと、情シスの現場を日々奔走している。
著書の詳細は、こちらをご覧ください。